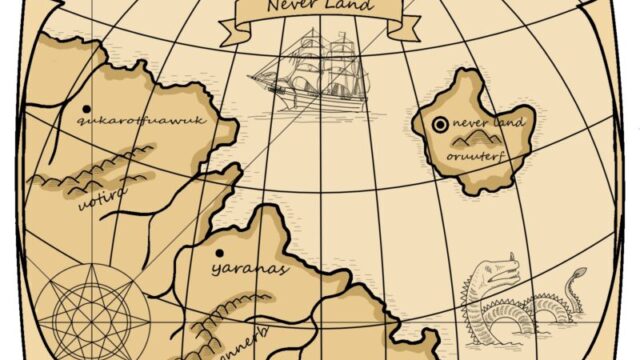那覇(飲み屋)に集まった人たち
客がそこには集まっています。しかも皆どこかよそよそしい感じがしています。何かの集まりではあるのですが、特に面識があるわけではありません。だからどこかよそよそしい雰囲気がただよっているのです。
乾峯人…西洋古家具骨董商を営んでいる、二十日鼠っぽい顔のアラフィフ男性
西貝計三…新聞社の記者で、酒が好きな赤ら顔のアラフォー男性
久我千秋…台北から来て都内のホテルに泊まっている、三十代半ばのイケメン男性
古田子之作…自動車修理工で、チャップリン髭をはやしているアラサー男性
雨田葵…すらりと背の高い二十代前半で、新宿のシネラリヤで働いている女性
の五人が店(那覇)に集まっています。
彼、彼女らはある目的があってこの店にやってきています。
なぜ集まったか、そして事件が発覚
各々、遺産相続について手紙や電話で連絡を受けて集まってきましたが、それなりに身に覚えはあるので、本当かどうか疑心暗鬼ではあるが、(それを欲というのかもしれないが)この場所にやってきました。しかし、それを説明する人物はこの店(那覇)には約束の時間を過ぎてもやってこなかった。
そうなると、この店の主人である絲満南風太郎が事情を知っているのではないかと思い、当人を呼んで来るよう話したが、店員は起こすといつも機嫌がわるいといって起こしに行くことをためらっていました。しかし、執拗に起こしてこいと言われて仕方なく起こしに行きましたが、部屋からは嫌な臭いがしてきたので警察を呼ぶことになった。警察が来て蝶番を外して部屋に入ったら、凄惨な状態で店の主人が倒れているのを発見しました。
それぞれが事件について推測
Bは警察に事情聴取といいつつ確保され、Cは犯人と目され執拗に尋問をされたが、これはある人物の密告がもとであった。しかも、それはただの推測に基づくだけのことでしかありませんでした。Bが証拠不十分で釈放されて、Aが密告したと聞かされたので、BがAのもとに復讐しに来ました。何でAが密告したかが分かったかといえば、Eがそう言ったのだとBはいい、Aはでまかせにやっぱり(他人を陥れようとした)Eが犯人だという。
Cを密告したのもAだった。どうやらEは警察の人間らしいともいう、DはCこそ怪しいと事件当夜に非常梯子をつたって戸外に抜け出したのを階下の住人が見かけたという。AはDも怪しいと、事件当夜に越中島でDを見かけ人がいるという。まさに情報が錯綜しています。
錯綜するなか、事件は終息に
AはBとCを密告し、Bは証拠不十分で釈放、DはCが怪しいと考え、EはCが犯人だと思い、CはEが犯人だと思い、F(新聞記者)もEが犯人と推理をします。このそれぞれが事件について推測することがかえって事件を混乱させてしまい、この点が物語として面白いところでもあります。
そしてある密告がおこなわれ、物語はクライマックスに向かっていきますが、本当の悪党たちが生き延びていくために他人を売っていくことでもあります。しかし、これは一面においては正しい密告であり別の事件の解決には寄与することになります。ですが、本筋である南風太郎の事件についてはむしろ解決とは逆方向に向かってしまいます。
久生十蘭のすごいところ
本当の悪党たちがどうなっていくのか、哀愁を感じつつ物語は終わっていきます。色々な人物の人生を絡ませながら物語を構成して、しかも破綻なくその設定を守りながらエンディングまで持っていっています。ミステリーというより、物語としての完成度が高いと感じます。
アリバイや動機についての考察、登場人物それぞれの秘密や素性を秘めさせて、恋愛についての心の機微も絡ませています。さらには別の事件について関連を持たせ、物語の幅、奥行きを出しています。だからこそ今もって久生十蘭の小説が読みつがれているのでしょう。
一番の感想は、ハードボイルドですね、です。